導入事例
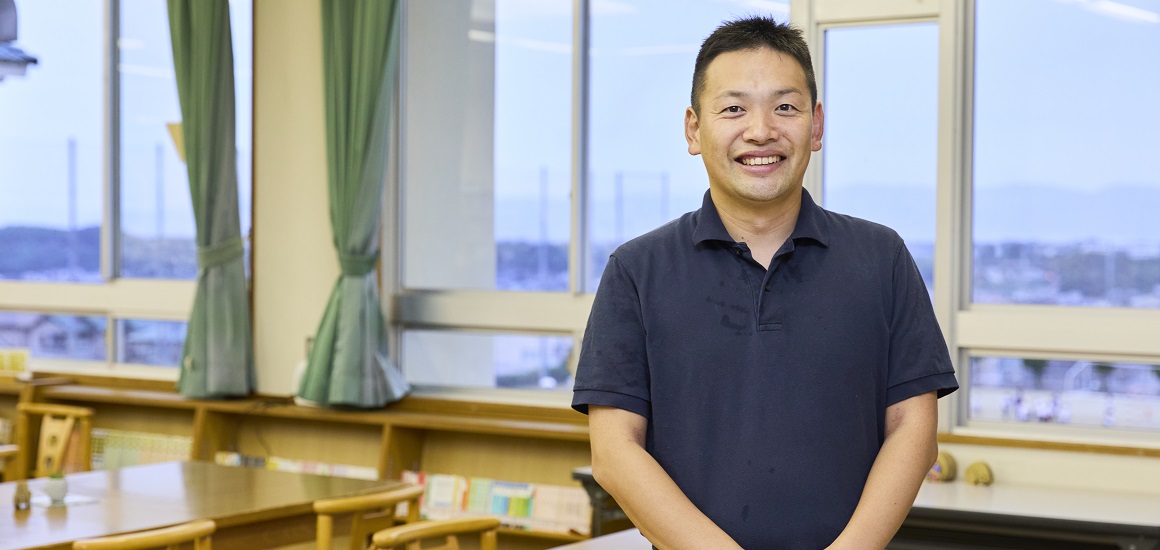
理解度を可視化し、
最適な指導へつなげる
- 取材
- 香芝市立香芝北中学校 | 関本先生
- 使用製品
- ドリルパーク
- 学年
- 中学2年生
ICT支援員の主体的なサポートによって、ミライシードを積極的に活用される先生・学校が徐々に増えてきているという奈良県香芝市。本日お話を伺う香芝北中学校の関本先生も、ICT支援員の大垣さんの進言から、担当の理科の授業や宿題でドリルパークを活用されています。生徒の理解度に寄り添った指導を大切にされている先生が、どのようにドリルパークを使いどのような効果を感じてらっしゃるのか伺います。
- 目的
- 既習単元の復習、知識定着の確認
- 効果
- ・生徒の取り組み状況が可視化され、すぐに授業内で全体指導や個別の声掛けができるようになった
・正答するまで繰り返し取り組めることで、子どもたちの理解が深まった
・家庭学習の課題を目的意識を持って、行うことができる
導入背景・目的
効果的に復習を行うツールとして、ICT支援員から提案されたドリルパーク
復習の授業で、子どもたちのつまずきを中心に理解補填したい
単元のおわりに設けている復習の時間で、子どもたちの「わからない」をできるだけ解決してあげたいと思っていたところ、ICT支援員の大垣さんが子どもたちのつまずきや理解度を把握するためのツールとして、ドリルパークの活用を提案してくださいました。問題の正答率や各生徒の取り組み状況をタイムリーに確認できることに加え、図表やグラフから視覚的に情報を読み取る必要が求められる理科の教科特性とも相性がよいと判断し、まずは授業で活用してみることにしました。

夏期休業中の課題など、授業以外での活用の提案も
本校では、夏休みにはいつも専用のワークを購入し、生徒の課題としていました。ただ、さまざまな理由から「丸写し」で形だけ終わらせるという子どもも少なからずいます。さらに、通常の教材に上乗せで購入してもらうため、保護者には金銭的な負担もかかってしまう。そういった課題感を持っていたところに大垣さんから背中を押され、今年はドリルパーク上で課題を配信し、夏休みに取り組んでもらうことにしました。

導入成果
気軽でありつつ、子どもたちの知識の未定着を見逃さない復習素材として役立っている
集計機能で可視化される情報を、即時で授業に反映
子どもたちがドリルパークを解いている中、同時並行でその取り組み状況や結果を確認しています。正答率を見てつまずいている生徒が多い問題はクラス全体に対して指導し、生徒一人ひとりの履歴を辿って進みが遅い子や、手が止まっている子がいたら個別に声をかけフォローできるようになりました。
「全部正答するまで解く」の実践で本物の力に
ドリルパークは、間違えた問題を何度も解き直すことができるので、私が出す課題においては全部正答するまで何度も解くよう子どもたちに伝えています。一方で、提出期日は長いスパンで設定し、問題を解くことが目的にならないよう配慮もしています。課題配信自体はとても簡単にできるので、夏休みの課題についてもすぐ用意することができました。ドリルパークの活用法、役割はまだまだあると思っています。2025年度の「全国学力・学習状況調査」で、中学校理科がCBT方式で実施されることもその一つです。デジタルでの演習に慣れておくことは、下準備にも繋がると思います。
子どもたちによりよい学びを提供するために、これからも信頼できるICT支援員と力を合わせてドリルパーク活用の道を拓いていきたいです。
※ページの内容は2024年10月時点の情報です。
使用製品
ドリルパーク個別学習ドリル
個々に合ったレベル・ペースで、知識の確かな定着や
主体的に個人で学ぶ姿勢を支援します。









 お問い合わせ
お問い合わせ