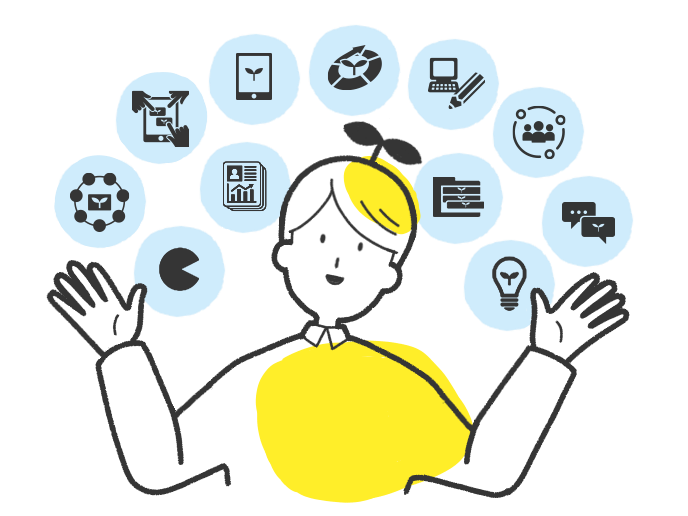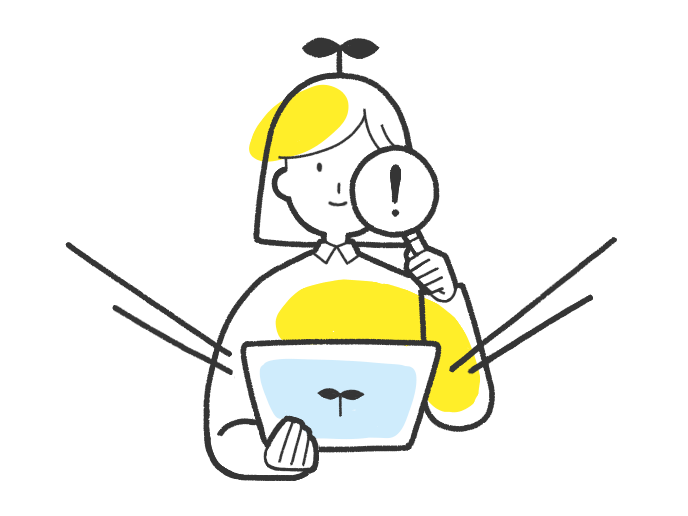やる気を失いがちな今、取り組みたい!「対話を生みだす」新着事例2選
11月は、年間を通しても学級の「荒れ」に注意が必要な時期だといわれます。
そこで今月は「対話を生み出す」新着事例を2つご紹介します。先生が一方的に指導や発信をするのではなく、子どもたち同士の対話を促すことで、主体性が引き出されます。新しいかかわり合いが広がるなかで、「自分たちの授業、クラスは自分たちで作る」という意識も芽生えるでしょう。
【実践1】ゲームで書き順や文字を見合う活動で、自然に対話が生まれ書字の意識向上!
普段の書写の授業は、子どもが書いたものを先生に見せて丸付けといったやり取りのみになりがち。 「オクリンク」の提出BOXを使ったゲーム形式の授業なら、子ども同士の対話が生まれ、なぜ書き順が大切なのか子どもたち自身で気づくことができます。[書き順クイズ]では、1画目を赤、2画目以降を黒で書き、提出BOXの一覧画面を共有して見比べれば、違いに気がついたり、「〇〇さん上手だね!」なんて声が上がったり。わざとおかしな書き順で書く[バラバラ書き順ゲーム]では、「変な形になっちゃう!」など、書きづらさを体感。最初、『書き順が違っても、書ければよい』という気持ちがあった子も、正しい書き順の友だちの字が整っているのを見て改められます。書く時のポイントに自ら気づいて、もっと上手に書きたい!と意識が高まる活動です。
活用事例記事はこちら
【実践2】一人ひとりに役割がある主体的な体験活動で、三角形の学びを深める
様々な三角形で内角の和が180°になることを理解するのに、「オクリンク」を使えば角度や色が異なる様々なパターンの三角形を用意するのに手間がかからず、体験の時間が増やせます。角度が書いてある三角形の内角を一人ひとつずつ配布し、3人で180°になるようにクラス内で交流しながら三角形を完成させる活動では、自分の持っている角度に役割があるので主体的に動け、「〇度の角が欲しいよ~」といった気づきの声が上がります。制限時間内にグループになれた子にはその理由をグループで確認、なれなかった子にはあと何度の角が必要だったか考えてもらい、提出BOXで共有します。「どうしたら三角形ができるのか」という課題に、体験を通して主体的に図形の性質を学べる実践です。
活用事例記事はこちら
ほかにも【新着】の活用事例をご紹介!
「ミライシード ファンサイト」 内【活用事例】のページをぜひご覧ください。
https://bso.benesse.ne.jp/miraiseed/fansite/usecase/list.html