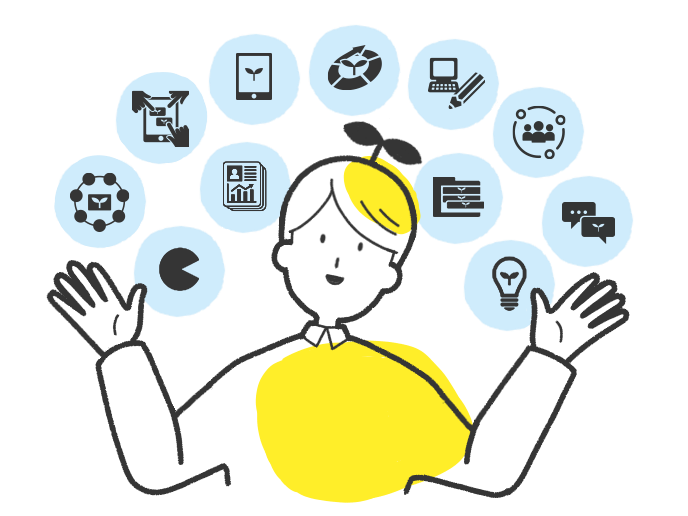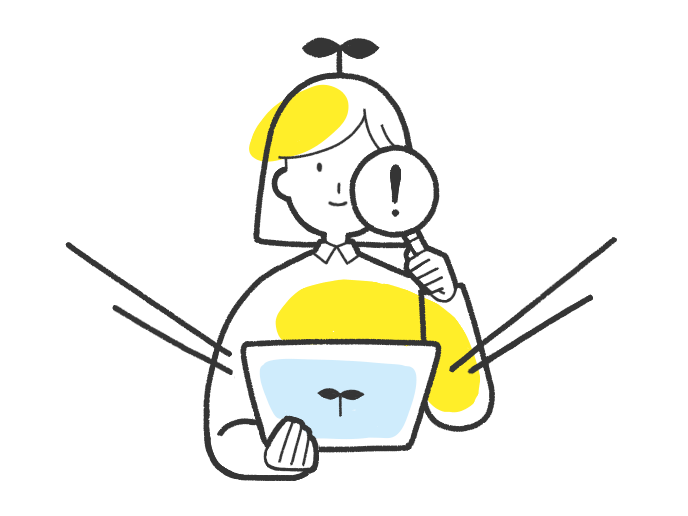夏休み明けの仕切り直しと効率化に使える2実践
長い夏休みも終盤ですね。夏休み明けの子どもたちは、これまでのクラスでの日々がいったんリセットされた状態です。これからの日々や学習が楽しみになるような、新しい仕組みやルーティンを定着させていくには一番よいタイミングではないでしょうか。
そこで今回は、クラス運営や授業での新たな仕組みづくりに使えるミライシード実践を2つご紹介します。
話し合い活動の「進め方」をクラス全員身につけられる
学級会もほかの教科のように経験が積み上がっていくと理想的ですよね。
「オクリンク」のテンプレートカードで議題や話し合いたいポイントについて事前に共有しておけば、子どもたちは自分の考えをもって学級会に参加することができます。
また、カードを提出BOXに提出することで全員の意見を一覧で見られるので、どんな意見があるのか把握しやすく、話し合いそのものやクラスの合意形成にじっくり時間をかけられます。
司会の子どもを変え同じやり方で回数を重ねることで、クラス全員が話し合いの進め方を身につけていける方法です。
(活用事例記事はこちら)
「ドリルパーク」で授業効率化 個別最適な理解定着を図る
授業冒頭の10分間を集中して「ドリルパーク」に取り組む時間として固定化します。
授業開始前に前時の学習範囲を課題として配信し、授業開始後に取り組ませます。その間に本時の板書をすると先生の板書を待つ時間もなくなり大変効率的。
「ドリルパーク」は、子どものトクイ・ニガテに応じた取り組みが可能ですし、先生は「リアルタイム進捗状況」で進み具合を一覧で確認できます。
理解度が見えるので授業内での課題解決が充実し、個別でのアドバイスも理解度に応じて対応可能。
子どもが思考する時間を、授業効率化で確保できます。
夏休みの課題に「ドリルパーク」を出された先生はぜひ、授業にも展開してはいかがでしょうか。
(活用事例記事はこちら)
いかがでしたか?
次回は9月15日頃に、子ども主体の授業実践をご紹介予定です。
ぜひお楽しみに!