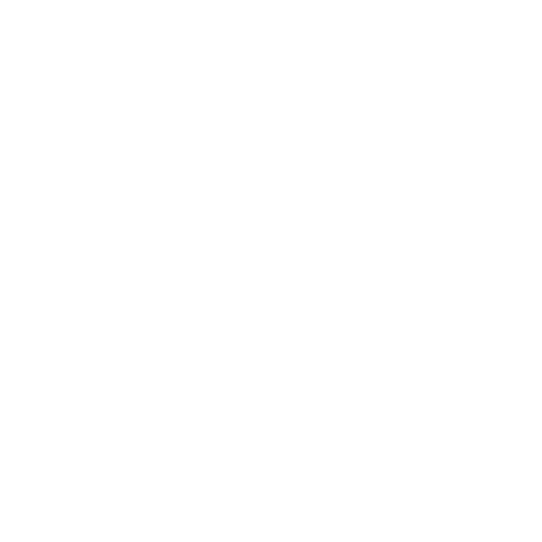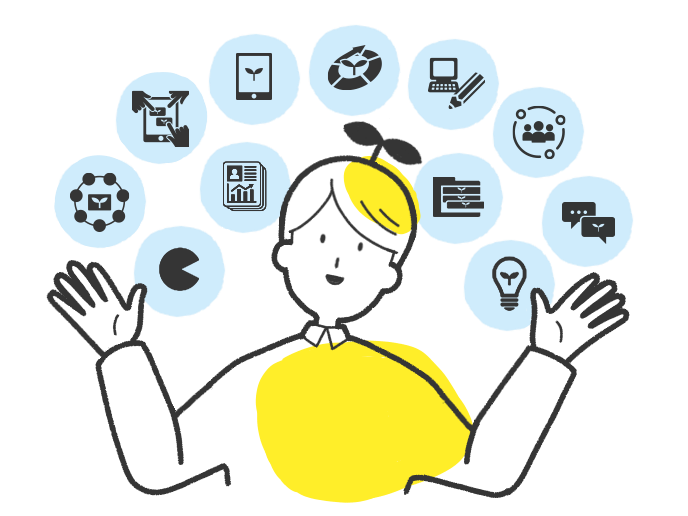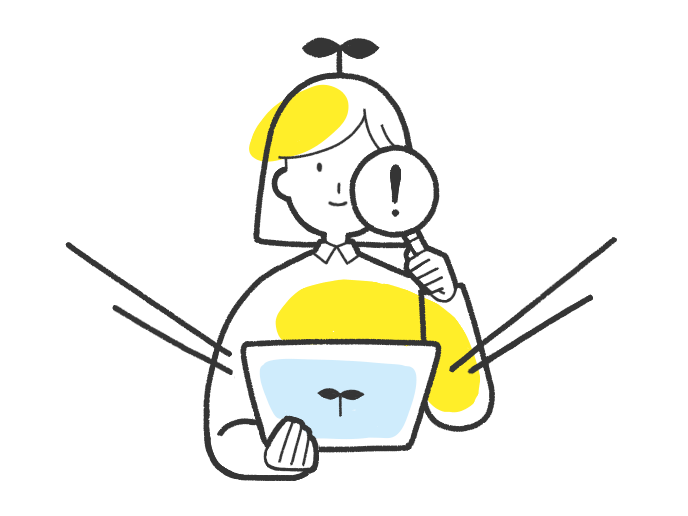子どもたちのことを思えば、
誰でも同じ方向を向いて
手を取り合って
やっていけるはずです。
——東彼杵町教育委員会、東彼杵町立彼杵小学校 、東彼杵町立千綿小学校 、東彼杵町立東彼杵中学校
縦横無尽に走る「線」の教育
町を挙げて子どもを見取る東彼杵町の実践
千綿小学校、彼杵小学校、東彼杵中学校の三校を抱える、長崎県東彼杵町。同町では、各校が主体的に学ぶ子どもを育成しようと、ICTを取り入れた実践に勤しまれています。2024ミライシードAWARDでも、驚くべきことに、全校から計5名もの先生にエントリーしていただきました。
東彼杵町の特徴は、単に各校の取り組みが進んでいるだけではありません。学校、学級、教科が垣根なく連携し、縦・横でつながりながら、授業改革を加速させている点こそ、同町の秀でた点です。
町全体の施策について同町教育委員会の山口厚教育長に、各校のお取り組みについて千綿小学校の中路校長先生・俵坂先生、彼杵小学校の吉永校長先生・山口先生・荒木先生に、東彼杵中学校の福田先生・松元先生に、それぞれお話を伺いました。
学校も、地域も、垣根を取り払って子どもを見守る
——教育長として、施策への思いを聞かせてください。
山口教育長:
私は教員時代から、教育にはなるべくたくさんの人が関わった方がよい、と常々考えていました。例えば社会科や総合的な学習の時間で、農業について学ぶとしましょう。教員は農業の専門家ではありませんから、農家の方に知識で敵うことはありません。だとしたら、農家の方を訪問したり、学校に招いたりして、巻き込んで学んだ方がよいですよね。子どもたちも、普段は接しない大人と接するときは、よく学びに関心を持つものです。ですから、学びはその学校に閉じられたものではなく、開かれたものであるべきだと考えています。
学校内に目を向けても同じです。私は小学校6年生の学級をよく受け持っていたのですが、管理職となったとき、それぞれの学年の積み重ねがあって、その時々の6年生たちが形づくられているのだとよくわかりました。それは縦のつながりであり、横のつながりでもあります。小学校なら担任が、中学校なら教科が変わったときに、全然学びが変わってしまうようだと、子どもたちは点でしか学べません。現場の先生方には、学校、学年、教科という縦・横の垣根を取り払い、縦横無尽の線をつなげて子どもたちを育む視点を持ってもらいたいと考えていました。

では、どうすれば垣根を取り払えるのか。例えば小学校と中学校は発達段階が異なりますから、「子どもたちに委ねよう」「しっかり心配しながら育てていこう」と、子どもを見取るスタンスに違いが生じます。他にも、教科担任制など、様々な違いがありますから、そこからお互いに違和感を覚えてしまうのが一般的かもしれません。ただそれは、単に交流が不足していて、互いの理解が進んでいないだけなのです。
同じ方向を向いて、日頃から交流していれば、手を取り合って子どもを育むことは十分可能です。そのために、私たち教育委員会は交流の素地をつくることに努めています。例えば、外部の方を積極的に紹介する。頻繁に学校に訪問したり、ペーパーやデータで各校の指導事例・研究事例を共有する。先生方が、自分の学校外の出来事や人に関心を持つよう、促しています。
さいわい、本町は以前から地域の方が非常に教育熱心で、保護者の方しかり、一般の方しかり、みんなで子どもを育てていこうという気概を持ってくれています。先生方の意欲も高い。私たちの意図通り、縦・横のつながりから授業を改善しようと日々の授業に臨んでくれています。何より、いつ・どの学校に伺っても、みなさん楽しそうに授業を行っていますね。だから子どもたちも楽しそうに学んでいます。授業が楽しくなれば学校が楽しくなる。実際に、2024年度は不登校生が減り、特に中学校は新たな不登校生が0でした。先生方の授業改善のおかげでしょう。
今、東彼杵町の教育は、縦・横のつながりを軸に、どんどんブラッシュアップされています。これからも、子どもたちのために、町全体で教育を手がけていく所存です。
ICTを活用し、子どもたちを“待つ”“見る”授業
——校長先生として、千綿小学校で力を入れられているお取り組みをお聞かせください。
中路校長先生:
先生方には「授業で勝負」といつも話しています。本校の子どもたちはとても素直で、教員が努力するほど、心を寄せて、力を蓄えてくれます。逆に手を抜くと、すぐにわかる。「わかった」や「できた」、「授業、もう終わったの?」といった声がたくさん出る授業を目指してがんばろうと伝えています。
先生方は、私のこうした気持ちによく応えてくれています。私は校長1年目で初めて東彼杵町に赴任しました。最初は驚いたのですが、職員室はいつも「あの子、ここまでできるようになったよ」と、子どもたちの明るい話題で盛り上がっています。本校は単学級学校で、1学年1学級しか設けられていません。各学年が自由に運営できるよさもありますが、だからこそ先生方が悩んでしまうときも多いはず。本校の先生方は、そこを「他学年だから」と切り離すことなく、学年を越えてみんなで子どもを見守っています。

——これから力を入れられていきたい、課題は何でしょうか。
中路校長先生:
教育長がお話されたように、東彼杵町は町全体で子どもたちを見守っています。一方で、これまでは学ぶことや学び方を、その見守る大人たちが先回りして決めすぎていたのではないか、と感じています。これからは、大人たちがもっと“待ち”、子どもたちに“委ねる”ように、見守り方を変えていく必要がありそうです。本校では、俵坂先生がそうした“待つ”“委ねる”授業を率先して進めてくれていますね。
——俵坂先生の授業を拝見しました。先生が細かく指示を出すのではなく、子どもたちの気づきを起点に授業を展開されていたのが印象的でした。
俵坂先生:
最近は特にですが、子どもをよく“見る”ことに注力しています。例えば今日はオクリンクプラスで思考ツールを使った授業を行いましたが、全体の提出状況を見ながら、子どもたちがわかっているか、わかっていないかをよく“見る”。わかっていないけど、まだ一生懸命取り組んでいる子がいるなら、いったん待ってみる。逆にすでによい内容を提出してくれている子がいたら取り上げて、その子を起点に他の子を引っ張ってあげる。こうして子どもが中心の授業をつくっています。

俵坂先生の授業の様子。子どもたちを“見る”ことにこだわられている。
アナログの場合、ここまで細かく一人ひとりの生徒の様子を見て、その場その場で授業を構成するのは難しかったでしょう。ICT活用が効果的だなと感じる場面の一つです。
 左から中路校長先生、俵坂先生。
左から中路校長先生、俵坂先生。
子どもたちも、教員も、協働で学びに向かう
——彼杵小学校の教育方針や課題感をお聞かせください。
吉永校長先生:
本校が最も力を入れているのは「学びに向かう力」の育成です。教育長がお話された通り、学びに向かう力が身につけば、学校や学級はどんどん落ちついていきます。児童は廊下を走らなくなり、スリッパもきれいに並ぶ。まだ道半ばではありますが、本校に荒れた部分は一つもありません。

吉永校長先生。先生からは、「学びに向かう力」の重要性を伺った。
——学びに向かう力の育成において、ICTはどのように貢献していますか。
吉永校長先生:
ICTを活用することで、教員が指導に終止してしまうのではなく、見取りまでしっかり達成できるようになりました。「この子はここまでできている」「この子は今悩んでいる」とリアルタイムで簡単にわかりますから。結果として、先生方が子どもたちを見る目も養われました。
また、子どもたちの学び合いも活発になりました。子どもたちは様々な個性を持っていて、算数が得意な子もいれば、国語や体育が得意な子もいます。苦手な教科は、得意な子に教えてもらう。学び合いが盛んになれば、授業中、誰かが取り残されることはなくなるでしょう。すると、自ずと子どもたちは落ちつきを得て、学びに向かう力がさらに高まっていくでしょう。
 授業の様子。どの子も、真剣かつ、楽しそうに端末に向かっていた。
授業の様子。どの子も、真剣かつ、楽しそうに端末に向かっていた。
実際に、2024年度は特に生徒指導事案が減りました。おかげで先生方は子どもたちの学びや授業づくりに集中できています。職員室からも、よく笑い声が聞こえるようになりました。これが私は、本当に嬉しくて。たまに覗くと、「あの子頑張っているよね」「応援したいよね」と、子どもたちのことでコミュニケーションを深めているんです。ICTの活用をきっかけに、子どもたちはもちろん、先生方も、学びに向かう力や環境がどんどん整っていっていると感じています。
——本日は2年担任の山口先生と4年担任の荒木先生の授業を拝見しました。オクリンクプラスを活用される際に、大事にされているポイントをお聞かせください。
山口先生:
私はよく、自分の意見を発する際のツールとして、オクリンクプラスを活用しています。同じ意見を発する活動でも、ノートに書くのと、提出BOXの画面を映し出されるのでは緊張感が変わります。オクリンクプラスを使うと、多くの児童が“人に見られる”ことを意識して、「しっかり考えなきゃ」と頑張ってくれますね。
もちろん、自分から意見を発するのが苦手な子や、うまく言葉で表現できない子もいます。そうした子でも、スタンプを活用すれば、友達の意見に簡単にリアクションできる。自分が何かアクションできたと思えるから、自信につながっていると思います。
 山口先生。荒木先生と一緒に、研修を手がけるICT部を運営している。
山口先生。荒木先生と一緒に、研修を手がけるICT部を運営している。
荒木先生:
オクリンクプラスは児童に何かを考えさせる際に、補助的に活用することが多いです。例えば今日も、「チラシAとチラシBのどちらが魅力的か」を考える授業を行ったのですが、オクリンクプラスを使うと、「AとBの違いを分類する」「意見を書き込む」など、すべての児童が何かしらの活動を絶対にできるんですね。ノートやワーク、プリントだけだと敷居が高い活動でも、オクリンクプラスならワンステップずつ手と頭を動かせるので、考え続けるハードルが下がったと感じています。
 荒木先生。荒木先生によれば、研修をきっかけに、校内の雰囲気が変わったそう。
荒木先生。荒木先生によれば、研修をきっかけに、校内の雰囲気が変わったそう。
——山口先生と荒木先生は、校内のICT活用の推進役でもあると伺いました。
山口先生:
もう1名の先生と一緒にICT部という研修部を設けて、毎月ミニ研修会を実施しています。ミライシードやTeamsの基本的な操作から、学級通信でのTeamsの活用法、ミライシードの新機能、それからICTを活用した授業例と、様々な情報発信に取り組んでいます。
荒木先生:
表立ってICTを説明する時間を設けたのは、とても効果的でした。というのも、研修会以外の場でも、先生方が質問してくれるようになったんですね。私たちも、普段の業務中に出しゃばって「ここはこうですよ」と言いづらいものです。互いに質問やアドバイスをしやすい雰囲気が生まれ、ICT部が関わらない場面でも、先生同士の学び合いが見られるようになりました。

教科の壁を破るカギは「子どもたちを輝かせる」こと
——東彼杵中学校では、社会科の福田先生と、国語科の松元先生の授業を拝見しました。お二人が授業で大事にされている価値観をお聞かせください。
福田先生:
私は社会科の教員ですので、生徒が自分の町を含めて、世の中に関心を持つきっかけとなる授業をつくりたいと考えています。生徒が他の地域の方に「東彼杵町ってどこにあるの?何があるの?」と聞かれたら、しっかり話せるようになってほしい。自分の言葉で発信してほしい。そうした生徒の育成を目標としています。
といっても、中学校の社会科は好き嫌いが非常に強く分かれるんですね。社会科が好きな子は、例えば特定の時代の歴史について教員以上の知識を持っていますし、一方で嫌いな子は教科書の字も見たくない。だからこれまでは、生徒に社会への興味を持たせ、自分の言葉で何か表現させるというのは、難しい部分もありました。
 福田先生。ICTの活用には不慣れだったそうだが、授業では非常に優れた活用を見させていただいた。
福田先生。ICTの活用には不慣れだったそうだが、授業では非常に優れた活用を見させていただいた。
ところが、オクリンクプラスを活用すると、子どもたちは率先して意見を表現するんですよ。全然嫌がらない。意見を表現することのハードルが低いんですね。紙に書くのと違って、きれいにレイアウトできるし、文字もタイピングするだけでいい。今まで全然積極的でなかった子が、率先して意見を表明するようになったのを見て、「これは使えるな」と強く感じました。
正直ICTは苦手でしたし、新しいことなんて覚えられないと思っていました(笑)。ただ、松元先生やICT支援員さんが積極的に教えてくださって、「やってみましょう!」と言ってくれるものですから、勇気を持って試してみました。実際は操作も簡単で、試してみて本当によかったです。現在は教科の授業に限らず、学校行事や学活の時間でも、積極的にICTを活用しています。社会科と同じで、子どもたちからの情報発信が積極的になりましたし、何より手書きでアウトプットするよりもスムーズですから、本質的な活動に時間をかけられるようになりました。
松元先生:
私が担当している国語科は言葉を学ぶ教科です。言葉に関する知識・理解は口に出したり、書いたりしないと身につきません。口に出して、書いて、そして間違ってまたインプットする。その繰り返しで、初めて自分だけの表現が磨かれていきます。ですから、子どもたちには口酸っぱく、「間違っていてもいいから、自分の言葉で表現しよう」と伝えています。
そうはいっても、福田先生と同じく、ジレンマもありました。多感な時期の子どもたちですから、わかっていてもあえて表現しない子はいます。もちろん、もともと表現するのが苦手な子も。ただ、私はそれを、表現してもらわないと把握できません。何とかして、子どもたちが自分から表現し、その表現の中で力を磨いていく仕組みをつくりたいと考えていました。

福田先生が話したように、ICTを活用してから、子どもたちはよく自分の考えを表現してくれるようになりました。加えて、さらに2つの変化がありました。一つ目は他者参照が容易になったこと。以前はよく付箋に考えを書き出して廊下に張り出していたのですが、ムーブノートやオクリンクプラスを活用するようになってから、学級間や学年間で、手間なく意見を共有し合えるようになりました。二つ目は、多様な学習の履歴が残るようになったこと。生徒たちは、私が言わなくても、以前の授業のマイボードを見て「あのとき、友達から何をコメントされたっけ?」「あの子はどうしていたかな」と、自己や他者から様々な学びを得て、その場の授業に学びを還元しています。特に他者の表現から学びを得直すのは、紙と黒板だけだとなかなか実現できないことでしょう。
 東彼杵中学校の授業の様子。画面上ではもちろん、対面でも盛んに協働が行われている。
東彼杵中学校の授業の様子。画面上ではもちろん、対面でも盛んに協働が行われている。
——福田先生は松元先生からも影響を受けたとお話されていました。中学校の場合、教科が壁となってなかなか校内の実践共有が捗らない場合もあると思いますが、いかがでしょうか。
松元先生:
本校は教室の廊下側の窓が透明なガラスで、授業の様子が筒抜けになっています。授業中、他教科の先生がふらっと来て、見学していかれることは多いですね。
福田先生:
職員室でも、当たり前のように授業や子どもたちの話をしていますね。そこに教科は関係ありません。職員室の雰囲気も、重要かもしれません。
松元先生:
加えて、どの先生も、子どもを中心に考えられているのが大きいでしょう。私も、子どもたちが国語以外の教科で頑張っていたら、それだけで嬉しいですから。使っているICTは同じなのですから、「どうすれば子どもたちが輝く授業がつくれるか」と、子ども中心の視点さえ揃えば、中学校の校内推進はもっともっと進んでいくのではないでしょうか。

【編集後記】
三校を訪問して印象的だったのが、どの学校も先生方が明るく、密にコミュニケーションを取っていること。取材中も、口を揃えて「先生同士の仲がいい」「職員室の雰囲気がいい」とお話されていました。また、本当に学校間の垣根がなく、中学校の先生は小学校の授業を、小学校の先生は中学校の授業を、それぞれ参考にされていたのも驚きでした。
先生同士の連携に加えて、教育長や指導主事、地域の方、そしてICTサポ―ターも、頻繁に各学校を訪問しているそう。まさに、町全体が一体となって教育に向かっている自治体でした。
撮影/株式会社 デザインオフィス・キャン 加藤武
取材・文/株式会社オンソノ 鈴木康介
※取材の内容は2024年12月時点の情報です。
※掲載にあたり一部の図版を編集しております。
所在地:長崎県東彼杵町
学校名:東彼杵町立彼杵小学校、東彼杵町立千綿小学校、東彼杵町立東彼杵中学校
特色:全校から計5名の先生が、2024ミライシードAWARDにエントリー。学校内はもちろん、教育委員会をハブに小学校・中学校が互いの授業を参考にし合って、町全体で切磋琢磨しながらICTの活用を深めている。